English
東工大 原子力系 - MIT学生交換プログラム 実施報告

本学 工学院、物質理工学院、環境・社会理工学院の3学院は、マサチューセッツ工科大学(以下MIT)原子力科学工学科との間に単位互換、授業料不徴収を伴う学生交換プログラム を発足させ、2020年1月に第1期 派遣・受入の実施が無事終了いたしました。
プログラム概要
東工大生、MIT留学生とも、派遣時は学士課程4年生であり、東工大生はMIT原子力科学工学科に所属し秋学期(8月~12月中旬)で学修します。MIT留学生は本学の第3、4クォーター(9月~翌年1月末)にて原子核工学コースで学修します。派遣先大学で所定の必須科目を履修する以外は、興味ある科目を選択することができ、さらに、研究室に所属し、教員より直接研究指導を受けることが可能です。 その他、派遣先国の文化や風土を体験する機会の提供や、交換留学の特色を生かしたネットワーキングイベントも実施しました。
プログラム実施に至る経緯、これまでの交流状況
本プログラムはMIT先進原子力エネルギー研究センターと本学科学技術創成研究院(先導原子力研究所担当)の間で2017年2月に更新締結した部局間協定(2006年に旧原子炉工学研究所と先方間にて当初締結)を基礎としています。原子力エネルギーシステムを共通の研究対象とし両学の研究交流、研究者、学生の継続的な交流を積んできましたが、2019年ついに学生交流に特化した本プログラムを設置し、このたび第1期の東工大生およびMIT留学生の約5か月間にわたる留学が無事終了しました。

12月5日 プログラム実務担当者間打ち合わせ 於MIT原子科学科 MISTI/ MITジャパン・プログラムマネージャー ピルカベージさん(最左) 原子力科学工学科 ショート准教授(右から3番目)

2月12日 プログラム代表者会談 副総長 ウェイツ教授(右から3番目) 理事・副学長 水本哲弥教授(左から3番目)
参加学生の体験談
| 派遣学生 | 佐藤 八起さん |
| 本学所属 | 環境・社会理工学院 融合理工学系 学士課程4年(参加当時) |
| 履修科目 | 1. 原子核工学および放射線相互作用概論 (Introduction to nuclear engineering and radiation interaction) 2. 放射線相互作用、管理、測定 (Radiation Interactions, Control, and Measurement) 3. 写真およびメディア関連概論 (Introduction to photography and related media) |
| 指導教員 | (履修指導担当)マイク・ショート教授 (研究指導担当)ブノア・フォルジェ教授 |
| 研究題目 | 核データの評価手法(WMP)においての誤差伝搬について |
| 研究概要 | Undergraduate Research Opportunity Program (UROP)にてOpenMCというモンテカルロシミュレーションコードを用いてのサンプリングとその解析を行うというのが元々の計画であったが、原子力科学工学科所有のクラスターへの開発環境のインストールが難航し時間切れとなってしまった。最終的には各核種における共分散マトリックスの計算手法を把握するができた。 |
プログラムに参加しての感想:
MITの講義はタフだ。1科目につき、週5時間分の授業に加え、平均7時間以上かかる課題が毎週課され、加えて予習のリーディングが山ほど出る。MITの学生はこれを5つも6つも履修するらしいので驚いてしまう。私は3科目+研究を履修するので精一杯だったが、学んだ知識は確実に自分のものになっている。厳しい学期をやり抜いたことは自分の自信につながっている。 プログラム参加において最も重要なのは、好奇心を大切にするということだ。MITでは学びの機会が十分すぎるほどにある。専門だけに限らず、他の文化的活動も盛んだ。また、街全体に学生を応援するような雰囲気がある。そのため、街にも学びの機会は多くある。それらを最大限に生かすには好奇心が必要だ。無機質な部屋に閉じこもっているよりは、外へ出て好奇心に従って行動した方が、充実した日々を送ることができるだろう。幸いにもボストンは文化的活動をするにはもってこいの場所だ。キャンパスからほど近い場所には美術館や科学館があり、街の中心にはアメリカの歴史を堪能できるスポットがいくつもある。好奇心に従って大いに学べば、この留学は非常に実り多いものとなるはずだ。
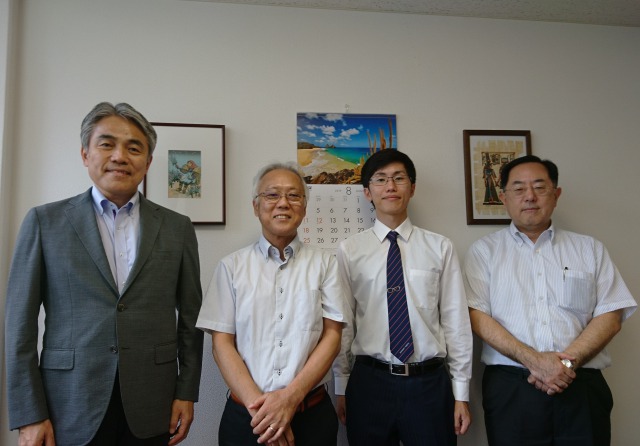
壮行会にて(右から2番目が佐藤さん)

新学期オリエンテーションにて(前列最左が佐藤さん)
| 受入学生 | エバ・リソウスキーさん |
| 在籍大学 | MIT 原子力科学工学科 学士課程4年 |
| 本学所属 | 環境・社会理工学院 融合理工学系 |
| 履修科目 |
|
| 指導教員 | (履修指導担当)小原徹教授 (研究指導担当)相樂洋准教授 |
プログラムに参加しての感想:
- 研究室での活動について 相樂研究室に所属し核不拡散に関わる研究などでMITでは体験できない多くの有意義な知見を得ることができた。毎週ゼミに参加し、仲間の研究進捗や日本の核不拡散研究の最新ニュースを学ぶことができたのは大変楽しい時間でした。
- 学習成果や研究成果について 授業では、日本の核エネルギーへの展望を学ぶ数多くの機会に恵まれました。また、日本語を話す能力を向上する機会もありました。学習成果としては大成功であったと思います!
- 日本での経験について 弓道、秋の鎌倉散策、生け花、おせち料理、茶道、空手など様々な角度から日本の文化を体験する機会に恵まれました。たくさんの友人を作ることができ、日本語を練習がてら、日本文化を学ぶことができました。
- プログラムに参加して、進路選択に何か影響はあったか 将来は、日米政府間または核エネルギー研究に従事したいと思っています。
- 留学先として、日本を選んだ理由 現時点で、日本は核エネルギーに対しとても興味深い視点を持っています。2011年の福島第一原子力発電所事故以来、電子力発電所は閉鎖しています。しかし、エネルギーセキュリティーの必要性やクリーンエネルギーの目的からも核エネルギーは日本にとって重要であると信じています。私は、この課題を学び、将来どのように日米が核エネルギー研究を協同できるかを確かめたいと思っていました。
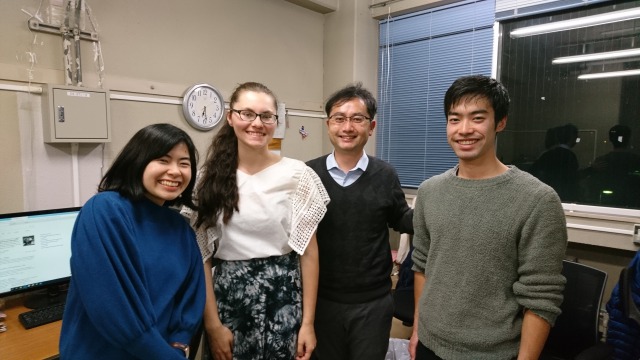
所属した研究室にて左から2番目がエバさん、右から2番目が相樂准教授)

目黒区国際交流協会主催の生け花体験イベントにて
内線: 3969Email: mitp.admin@jim.titech.ac.jp 居室: 本館2階227号室